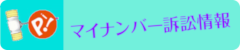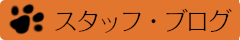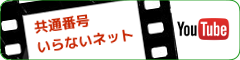post by nonumber-tom at 2018.9.14 #235
 個人情報保護委員会 ヒアリング
個人情報保護委員会 ヒアリング
個人情報保護委員会へのヒアリング報告 (2)
事業者の取得した個人番号の利用目的変更のQ&Aについて
個人情報保護委員会は、2017年5月の地方税特別税額決定通知書の発送を前に、地方税事務のために通知したマイナンバーの他の事務への「使い回し」を認めるガイドラインのQ&Aを追加しました。金融機関でも同様の扱いを認めています。
このQ&Aは自己情報コントロール権を侵害しマイナンバーの不正利用を助長しないか、個人情報の保護より利活用を重視しているのではないか、委員会に質しました。
このQ&Aは自己情報コントロール権を侵害しマイナンバーの不正利用を助長しないか、個人情報の保護より利活用を重視しているのではないか、委員会に質しました。
(2)事業者の取得した個人番号の利用目的変更の
Q&Aについて
「Q&Aは変更ではなく
従来からの考え方を示しただけ」
住民税事務のために通知したマイナンバーの
「使い回し」を認めるQ&A
個人情報保護委員会は、2017年5月の地方税の特別税額決定通知書の発送を前に、3月29日に特定個人情報(個人番号の付いた個人情報)の取扱ガイドラインのQ&Aを追加しました。
通知に記載したマイナンバーは、本人にマイナンバーの利用目的を通知・公表していれば、その範囲内で地方税事務以外も利用できる(Q1-3-2)、本人以外から提供を受けた個人番号も提供元ごとに利用目的を特定する必要はない(Q1-3-3)という内容です1 。
個人情報保護委員会の回答は
個人情報保護委員会からは、追加は事業者から多く問い合わせがあった事項について載せており、従来からの考え方を示しただけで変更したわけではないとの回答がされました。
今回追加した理由は、通知した個人番号が地方税事務にしか使えないとなると、事業者がもともと保有している個人番号と事務ごとに別管理しなければならなくなる懸念があるためだという説明です。
たとえば地方税でしか使えないと、表裏一体の源泉徴収票という国税にも使えなくなり、利用目的を分けるのは負担だと考えたということです。
個人情報の保護より利活用を重視したのではないか
私たちは利用目的の特定・限定というプライバシー保護よりも、個人番号の使い回しを容易にするという利便性を重視して扱いを変更したのではないかと重ねてたずねました。それに対して委員会は、恣意的に利用範囲を広げるためにQ&Aを変更したのではなく、制度上もともと利用目的の変更は認められていて個人情報保護法は保護と有用性・活用という両面を持っており、委員会は厳しく取り締まるということだけではないと説明していました。
利用目的の明示を指導してきたことと矛盾しないか
政府はマイナンバー制度の開始にあたり、マイナンバーを本人から収集する際には利用目的を明らかにするよう指導してきました2 。それは単に個人情報保護法18条で個人情報取得の際には利用目的を本人に通知・公表することが決められているためだけではなく、マイナンバーの利用事務は法令で限定されており、それに反した利用が行われないよう確認する必要があるからです。提供した利用目的と違う目的で使われていくようになれば、不正な流用を助長するおそれがあります。
総務省は個人情報保護委員会などと協議して利用目的の通知を変更
総務省は当初2016年11月25日に、通知に記載のマイナンバーは番号法第9条第3項の規定により地方税事務以外には利用できない、という通知を送っていました3 。しかし2017年3月2日に、Q&Aと同様の内容に変更する通知に変更しました4 。
内容が変化した理由について総務省は、市区町村に番号法の規定をより正確に伝えるために個人情報保護委員会など関係省庁と協議して通知したものと説明しました。しかし2016年11月25日の通知が個人情報保護委員会などと協議して出されていたのかは、明確な説明はありませんでした。マイナンバーの使い回しを容易にするための変更ではないか、という疑いは消えません。
預貯金口座への付番でもQ&Aを変更し使い回し可能に
利用目的を変更して預貯金口座への付番に「使い回し」を認めるQ&A
2018年1月から預貯金口座にマイナンバーの付番がはじまりましたが、金融機関等へのマイナンバーの提供は、法令上、義務ではありません5 。
個人情報保護委員会は、預貯金口座への付番のQ&Aを2017年7月に追加し、個人番号の提供を受けた時点で利用目的としていなかった「預貯金口座への付番に関する事務」にも、変更された利用目的を本人に通知または公表すれば利用可能としています6 。そのため金融機関ではマイナンバーの利用事務を掲載したホームページに「預貯金口座への付番に関する事務」を加えることで、金融機関内でマイナンバーを預貯金口座への付番に使い回しています7 。
このQ&Aを追加した理由も個人情報保護委員会は、問合せがあった事項を追加したもので金融機関から事情を聞いて作成したと回答しています。しかしこれでは、預貯金口座への付番のためにマイナンバーの提供をしたくない人も、勝手に付番されてしまいます。
行政から金融機関にマイナンバーを提供し付番に利用?!
さらにある識者は、今後役所などの口座振込申請書にマイナンバーの記載欄が追加される予定で、役所から金融機関にマイナンバーが提供されるのでそれを預貯金口座への付番に流用できると説明しています8 。そうすると本人は金融機関にマイナンバーを伝えていなくても預貯金口座に付番されてしまい、提供は義務ではないとしていることがまったく無意味になります。
普及率が11%に低迷しているマイナンバーカードを作りたくない理由として、預貯金を税務署に知られたくないなどプライバシーが漏れることへの不安があります。金融機関へのマイナンバーの提供はあくまで任意であるべきです。
しかしこれについても個人情報保護委員会は、制度上、利用目的の変更は認められており、事業者がそれをどう表示していくかは対顧客の関係だという形式論で認めていました。ただヒアリングに出席した金融庁の担当者からは、おっしゃるところはよく分かるが、金融庁として口座振込申請書へのマイナンバーの記載欄の追加を検討していることはまったくないとの説明がありました。
次のページ : »(3)情報提供ネットワークシステムの監視は行われているか?
Note
» 今回のヒアリングのために個人情報保護委員会に提出した質問書
» 前回質問書への回答拒否に対する、個人情報保護委員会あて抗議声明
*1 : » 「マイナンバーについて ガイドライン Q&A(回答)」 事業者編 1:個人番号の利用制限 Q1-3-2。個人情報保護委員会
*2 : » 「マイナンバー(社会保障・税番号制度) よくある質問(FAQ)」 4-2 マイナンバーの取得 Q4-2-3。内閣府
*3 : » 「平成29年度分以降の個人住民税に係る特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)の送付に関する留意事項について(通知)」 総務省自治税務局市町村税 課、2016.11.25
*4 : » 「平成29年度分以降の個人住民税に係る特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)の送付に関する留意事項について(通知)」 総務省自治税務局市町村税課、2017.3.2
*5 : » 「番号制度概要に関するFAQ」 その他 Q3-14-2。国税庁
*6 : » 「マイナンバーについて ガイドライン Q&A(回答)」 【(別冊)金融業務】 16:個人番号の利用制限 Q16-5。個人情報保護委員会
*7 : たとえば、三菱東京UFJ銀行の例として » 「個人情報の利用目的の改定について」 株式会社三菱東京UFJ銀行、2017.7.18 などを参照
*8 : 『預貯金へのマイナンバー付番Q&A』 梅屋真一郎、ビジネス教育出版社、2017.10.24 p.34
photo素材:ぱくたそ ©axis

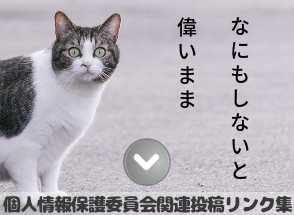
●2019.11.14
» 違法再委託によるマイナンバーの漏えいはどうなっているか
●2019.2.15
» 違法再委託問題で個人情報保護委員会に質問書
●2018.8.29
個人情報保護委員会ヒアリング報告
» (まとめ)個人情報保護委員会へのヒアリング報告
» (1) 住民税特別徴収額通知漏えいへの委員会の対応は?
» (2) 事業者の取得した個人番号の利用目的変更のQ&Aについて
» (3) 情報提供ネットワークシステムの監視は行われているか?
» (4) 日本年金機構の不適正な再委託にどう対応したか?
» 報告全文をPDFでダウンロード
●2018.9.14
» 個人情報保護委員会へのヒアリング報告
●2018.8.25
» 個人情報保護委員会ヒアリング&検討会
●2018.6.1
» 個人情報保護委員会に抗議声明
●2018.4.9
» 個人情報保護委員会 回答を拒否
●2018.4.9
» 個人情報保護委員会でマイナンバー制度の危険性は防げるか 2018年3月7日学習会報告
●2018.2.4
» 個人情報保護委員会へ質問書を提出しました(趣旨説明)
●2018.1.31
» 個人情報保護委員会へ質問書を提出しました
●2017.4.24
» 2017.3.3 省庁等交渉レポート最終回 個人情報保護委員会は機能しているか